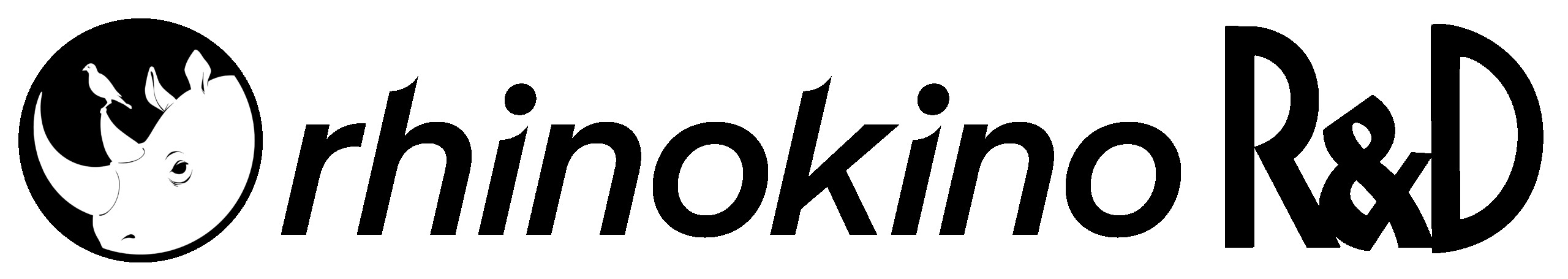Category
会場調査
調査対象者を会場に集めて、テスト品やコンセプトなどを呈示し評価を得る調査手法です。
試食・試飲・広告やコンセプト・店頭疑似購買など幅広く呈示品の評価を得ることが可能です。
効率的に多くのデータ収集が可能であり、会場内で調査が完了するので短期間で結果を得ることが可能な手法です。
インターネット調査では困難な、味覚や嗅覚・触覚を使っての評価が可能であり、且つ会場内という閉鎖空間での呈示であるため情報漏洩のリスクが低いことも
会場調査のメリットと言えます。
インターネット調査や個別調査に比べ、広い空間を用いるため疑似購買などもより現実に近い形で行う事も可能です。
セントラルロケーションテスト(Central Location Test)とも言います。

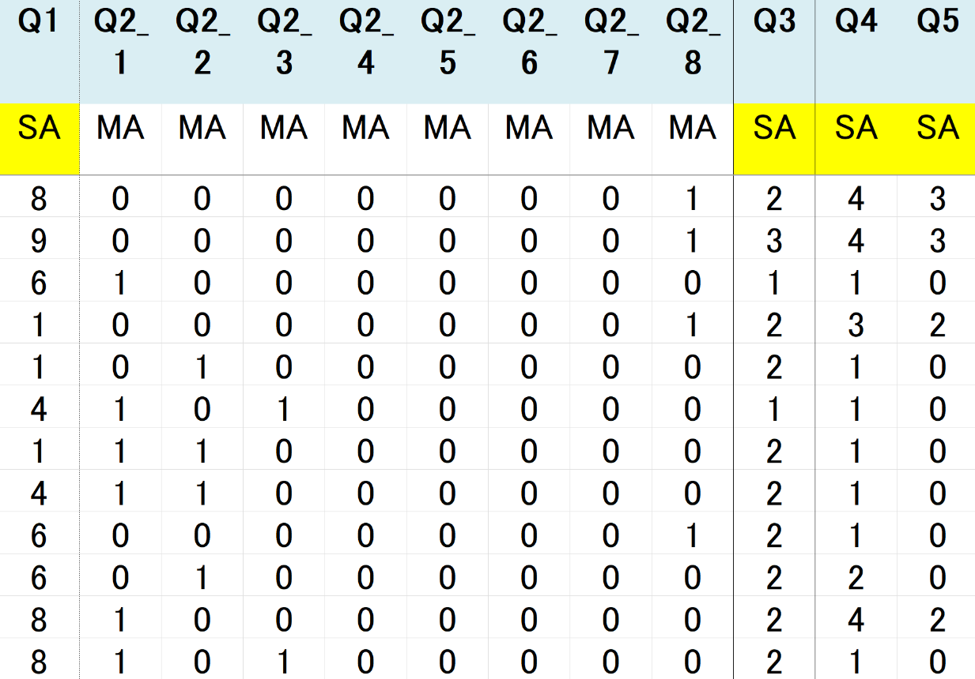

POINT 01
事前に詳しい情報を流すことができない機密性の高い商品やコンセプト・開発段階の商品なども、秘匿性を保持したままで多くのデータ収集が可能な手法です。
また、調査を行う製品と比較したい製品を提供する時に、テスト環境を統一して提供できることも会場調査の優れた特徴です。
温度管理や提供方法などにより、味や状態が大きく変わるような試飲・試食調査は、会場調査の得意分野でもあります。
また司会者を設置し、一斉に同時進行で調査を行えば、対象者への提示の時間差による微妙な相違もなくすことが可能になります。
POINT 02
要望に沿ったスケジュール設定、調査の効率や内容に沿ったキメ細やかな会場デザインと緻密なプランニング、そして厳格な試料管理により
より効率的により正確に実査体制を築くことが可能です。
対象者に対して的確な指示を行う事により、「コンセプト」「仕様」「味」「パッケージ」「ネーミング」などに関する反応を、ダイレクト且つ短期間で収集可能です。
ホームユーステスト
商品のサンプルや試作品を調査対象者に普段の生活の中で使用してもらい、その使用感や効果、使い勝手などから評価していただく定量調査です。
日々の生活の中での使われるモノや摂取されるモノのように来場型の調査では普段の環境下に無いために何らかのバイアスがかかり評価が困難なことがあります。
(朝や夜のルーティーンでの化粧品類や入浴、普段の生活のタイミングで服用しているサプリなどその他さまざま)
ホームユーステストでは、普段使用している環境下での試用が可能であるため、より日常的な場面での使用感などの情報を得ることが可能です。
但し、使用する環境が人それぞれ独自のものになるため、一定環境下での評価を得るためには会場調査を行うなど、手法の使い分けが必要です。



POINT 01
シャンプー・洗剤などの日用品、化粧品・美容用品・ヘアケア用品、飲料・食料品、アプリやゲームなども含め日常生活で使われるあらゆる製品について、日常生活下での評価を得ることが可能です。
開発中の製品の、特長・味覚的な評価などは会場調査でも取得可能ですが、ある程度使用しての使用感や効果などを見るためにはホームユースが最適です。
複数の試作品や競合製品と比較し、日常生活下においての比較評価も可能であり、より具体的な課題の抽出が可能です。
POINT 02
商品を購入した際、店舗では評価が高かったのに自宅に持ち帰って使用してみると印象が変わった、という経験はままあります。
ホームユーステストは、実生活に近い環境で使用した印象や評価を得ることができるので、店舗やインターネット上での情報と実際に使用しての評価に差異が生じる場合があります。
それらの際を埋めるための商品開発に役に立つ手法と言えます。
試用いただく商品の商品名やブランド名を非明示にすることで、ブランドイメージによるバイアスを取り除くことも可能です。
逆に、商品名・ブランド名・パッケージなどを明示することで、その製品の総合的な商品力を評価することも可能です。
どのような設定で試用評価を行うかにより、より消費者のニーズに近い情報を得ることが可能となり、魅力的な商品づくりを進めることが可能になります。
訪問調査
調査員が一般生活者の自宅や事業所を訪問し、調査を依頼し、調査票を使って対象者から直接回答を得る調査手法です。
調査員が対象者に直接聞き取り調査を行う「面接法」と、対象者に調査票を預け回答を記入してもらった後に再度訪問し回収を行う「留め置き法」があります。
事前に作成されたリストに沿って対象者宅を訪問する場合と、指定の調査エリアで条件に合う方を探して調査を行う場合があります。
訪問調査は対象者の方の顔が見えるので、インターネット調査とは違い、なりすましを防いだり機密性の高い調査を行う事が出来ます。
但し、訪問調査は調査員の教育やトレーニングの付加が大きく人件費や移動にかかるコストが高くなる傾向があります。
さらに近年では、一般家庭・事業所共に訪問を望まないケースが増え、特に一般家庭ではオートロックの普及や日中不在の家庭が増えているため調査を行うにあたっての弊害となっています。



POINT 01
調査員が直接対象者から回答を得る「面接法」においては、資料や商品を確認しながら聴取することができるため、確実に商品を特定して評価を得ることができます。
したがって、誤認などのリスクも減少し、また状況に応じて回答の掘り下げなども可能であるため、より柔軟な情報収集が可能です。
「留め置き法」では後日記入済みの調査票を回収するため、時間に余裕が無い方にも調査を協力いただけます。
POINT 02
訪問調査の成否は、調査員の質に大きく左右されます。
調査員は対象者の方との接し方や質問方法に関して、教育・訓練を受けます。調査を実施する前には調査員全員を集め、説明会を実施し「調査概要」「調査方法」「調査手順」などを周知徹底します。
必要に応じて面接訓練も行います。
説明会を行う事で、調査方法や手順を均一にすることが可能です。
調査実施に当たっては、回収票の管理や状況把握を行いスケジュール通りに調査票を獲得できるようにします。調査票回収後には内容の確認や調査実施の確認(インスペクション)も併せて行います。
どのような設定で試用評価を行うかにより、より消費者のニーズに近い情報を得ることが可能となり、魅力的な商品づくりを進めることが可能になります。
店舗調査
コンビニエンスストア・スーパーマーケット・デパート・ショッピングモールなどの店頭で行う調査です。
売り場レイアウトや商品陳列、価格、店舗内プロモーションなどの来訪者の反応や評価を現場で聴取することが可能です。
主に流通企業の自社店舗の評価や、流通現場での商品の取り扱い状況などをメーカが把握するために実施されます。
消費者の多くは、品揃え・POP・価格・売り場レイアウト・デモンストレーションなど店舗の各容認によって購買意欲に変化が生じます。
消費者と各種商品・サービスが出会う店舗や事業所でのマーケティングが、「商品購入・サービス利用」の決め手となりえます。



POINT 01
店頭調査はマーケティング課題によって様々な手法に分かれます。
1)出口調査
店舗出口にて来店者に調査を行い、来店客のプロファイルや来店動機・利用状況などのデータを収集することで、店舗の魅力や問題点
来店客の満足度などを把握し、今後のターゲティングや店舗の問題点を浮き彫りにし、今後の店舗づくりのために役立てられます。
2)顧客観察調査
調査対象者が、普段通り・もしくはある特定のタスクに従って買い物をする様子を観察した後に、一連の購買行動についてインタビューを行い、店頭購買プロセスにおける行動や意識・心理を探ります。
3)店内動線調査
調査員が来店客の店内での動きや各売り場への立ち寄り状況を観察することで、売り場レイアウトの問題点や来店客の動線を把握します。
それらにより、消費者が動きやすい・商品を探しやすい、そして購入に結び付きやすい店舗づくりに反映させます。
実際の来店者を観察する場合と、予め依頼した調査対象者の行動を観察する場合があります。
依頼した調査対象者の場合は、特定のタスクを設けることも可能です。
4)購入者調査
特定の商品を購入した方へ、購入後調査を依頼します。
売り場でその商品を選んだ理由や普段からの購入状況などを聴取できます。
但し、購入状況をチェックするため店舗の承諾が必要になります。
5)来店者カウント調査
各出入口で、性年代別にカウント調査を行います。
これにより、出入り口の年代別の利用状況や店舗内での店舗配置の計画性に役立でられます。
POINT 02
店頭調査の実施には、店舗の協力が必要です。競合店舗での実査は基本的にはできません。
調査依頼主から各店舗への協力依頼を事前に告知いただき、必要に応じて事前に各店舗の責任者の方へご挨拶を行う場合がございます。
事前のご挨拶の際に、当日の調査員の配置場所や対象者の方へ行う内容をご説明し、当日の店舗の営業に影響がないように調整いたします。
調査員の勤務時間・人数によっては、店舗内もしくは近隣に控室が必要になる場合もあります。